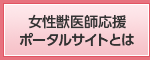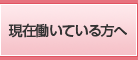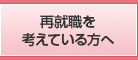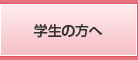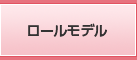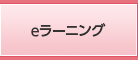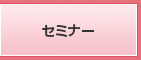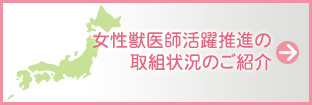獣医師生涯研修事業Q&A 小動物編(日本獣医師会雑誌 第78巻(令和7年)第6号掲載)
症例:雑種猫,去勢雄,4 歳
主訴:来院2 週間前より食欲・活動性が低下し,数日前から後肢に力が入らず,動きたがらないとのことで,精査のため当院を受診.
一般身体検査:体重5.7 kg(BCS 5/9),体温38.1℃,心拍数180 回/ 分,呼吸数40 回/ 分
血液検査・血液化学検査:CBC は著変なし.軽度高窒素血症(BUN 39.8 mg/dl,Cre 1.77 mg/dl)を認めた.
ウイルス検査:FIV 抗体及びFeLV 抗原陰性.
神経学的検査:四肢の姿勢反応の低下,右側前後肢の脊髄反射の軽度亢進,及び四肢の表在性痛覚の減弱が認められた.脳神経検査では異常は認められなかった.
胸部X 線検査:特筆すべき著変なし.
腹部X 線検査(図1):右腎の不整な形態と顕著な腫大を認めた.(第2 腰椎比:右腎4.1).図2 は腎臓の超音波検査画像,図3 は腎臓の細胞診である.
質問1:腎臓の超音波検査画像でみられる異常所見は何か.
質問2:治療上の留意点は何か.
解答
質問 1 に対する解答と解説:
本症例は,腎臓の超音波検査所見より腎臓型リンパ腫が疑われ,FNB による細胞診において,中~大型で核小体が明瞭なリンパ球が多数採取されたことから,腎臓型リンパ腫と確定診断された.本症例の腎臓の超音波検査所見としては,腎辺縁の不整,腎被膜下の低エコー帯,皮髄境界部における線状構造が認められた(図4).
猫の腎臓型リンパ腫において一般的にみられる超音波所見は,腎腫大(79%),形態の不整(75%),腎被膜下の低エコー帯(61%),皮質の高エコー源性(43%),腎盂拡張(32%)である[1].これらに加えて,皮質や髄質に線状あるいは点状の高エコー像がみられることもある.
中でも,腎被膜下の低エコー帯は,猫の腎臓型リンパ腫に特徴的な超音波所見であり,犬でみられることはまれである.この所見に基づく猫の腎臓型リンパ腫の検出感度は61%,特異度は85%と報告されている[1].この低エコー帯の形成には,腫瘍細胞の被膜下への浸潤や壊死,少量の液体貯留が関与していると考えられている.ただし,同様の所見は猫伝染性腹膜炎(FIP)に伴う腎炎や,リンパ腫以外の悪性腫瘍でも認められるため,これらの疾患との鑑別が必要である.
質問 2 に対する解答と解説:
本症例における治療上の注意点は,腫瘍崩壊症候群(TLS)のリスク管理及び中枢神経系への浸潤を考慮した治療プロトコルの構築の2 点である.
(1)TLS のリスク管理
腫瘍崩壊症候群(TLS:tumor lysis syndrome)は,大量の腫瘍細胞死によって細胞内のカリウムやリンなどが急激に血中へ放出され,代謝性アシドーシス,高リン血症,高カリウム血症などを引き起こす代謝性異常である.さらに,腎機能が障害されることで,高窒素血症を呈することもある.化学療法や放射線治療開始後に発生しやすく,特に腫瘍体積の大きなリンパ腫症例では発症リスクが高い.一度発症すると致命的になる可能性があるため,リスクの高い症例では治療開始前からの予防的管理が不可欠である.本症例では,顕著な腎腫大及び高窒素血症を認めており,治療初期におけるTLS 発生のリスクが高いと判断された.そのため,初回抗がん剤投与の前日より入院下で静脈点滴を実施し,慎重に経過を観察した.
(2)中枢神経系への浸潤を考慮した治療プロトコルの構築
猫の腎臓型リンパ腫は,中枢神経系への浸潤が比較的多い腫瘍型である[2].本症例においても,神経学的検査所見からは上位運動ニューロン徴候を示す脊髄病変が疑われ,多巣性あるいは広範な脊髄領域の関与が示唆された.本来であれば,MRI 検査や脳脊髄液検査による評価が望ましいが,本症例ではこれらの検査は実施できなかった.そのため,神経学的所見に基づき中枢神経系への浸潤を想定し,L-CHOP ベースのプロトコル(UW-25)を基本としつつ,中枢移行性の高い抗がん剤(例:シタラビンなど)を適宜組み込む方針とした.猫の腎臓型リンパ腫は,消化管型に次いで多い節外型リンパ腫であり,発症年齢の中央値は9 歳とされるが,1 歳未満の若齢例も報告されている[3].CHOP またはCOP ベースの化学療法による生存期間の中央値は4 ~ 7 カ月とされ,多くの症例では両側性の腎病変を呈し,他の腹腔内臓器への浸潤を伴うこともある.そのため,腎臓以外の臓器のスクリーニングも重要である.本症例においても,腎臓以外に中枢神経系への浸潤が疑われた.化学療法開始後,腎腫大及び腎実質の病変は改善し,神経症状は消失した.これらの反応から中枢神経系への腫瘍浸潤が実際に存在していた可能性が支持された.その後,治療開始から2 カ月後に再発を認めたため,L-CHOP プロトコルからレスキュー療法に切り替えた.化学療法剤として,中枢神経系への移行性及び有効性を考慮し,ACNU,L-アスパラギナーゼ,シタラビンを選択した.一時的な改善はみられたが,次第に効果は減弱し,診断から約5 カ月後に斃死した.
参考文献
- [ 1 ]Valdés-Martínez A, Cianciolo R, Mai W : Association between renal hypoechoic subcapsular thickening and lymphosarcoma in cats, Vet Radiol Ultrasound, 48, 357-360 (2007)
- [ 2 ]Mooney SC, Hayes AA, Matus RE, MacEwen EG : Renal lymphoma in cats: 28 cases (1977-1984), JAm Vet Med Assoc, 191, 1473-1477 (1987)
- [ 3 ]Vail DM, Pinkerton M, Young KM : Hematopoietic Tumors, Withrow and MacEwen’s Small Animal Clinical Oncology, 6th ed, Withrow SJ, Vail DM, Page RL, eds, 688-722, Elsevier, St. Louis (2020)
キーワード:猫,腎腫大,腎臓型リンパ腫,超音波検査,神経症状